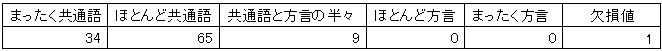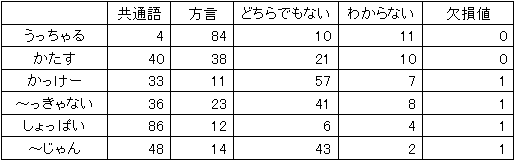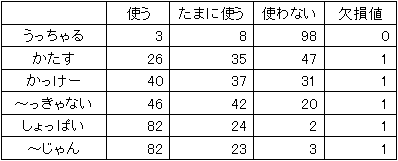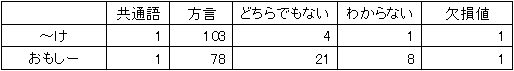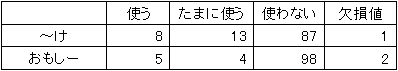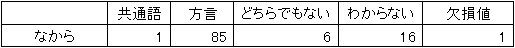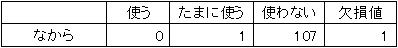関東方言に対する認識とその使用について
国文学科2年 高田晃
【調査のテーマ】
・東京の中学生は関東方言に対して、どれくらい認識をしているのか?
・実際にどの種類の関東方言が使われているか?
○自分の話していることばは、どの程度共通語または方言だと思いますか?
という質問に対して
【自分のことば】 表1 (109人中)
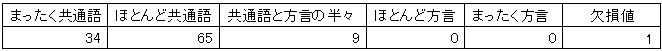
この結果から、ほぼ全員が共通語を話しているという認識のようだ。
○関東全域に広がる方言について
【認識】 表2 (それぞれ 人/109人中)
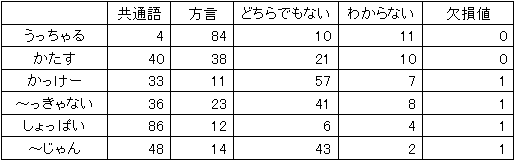
【使用】 表3 (それぞれ 人/109人中)
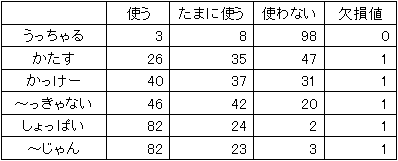
○東関東に広がる方言について
【認識】 表4 (それぞれ 人/109人中)
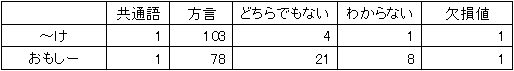
【使用】 表5 (それぞれ 人/109人中)
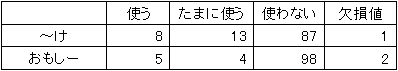
○西関東に広がる方言について
【認識】 表6 (それぞれ 人/109人中)
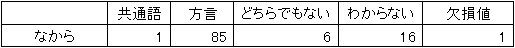
【使用】 表7 (それぞれ 人/109人中)
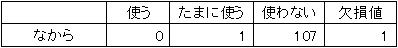
という結果が出た。
「表1」の【自分のことば】では、松沢中学校の2年生ほぼ全員が共通語を話しているという認識だったが残念、タイトルの通りこれらはすべて方言だったのだ!
これらを方言の種類で分けると、「関東全域」、「東関東」、「西関東」にそれぞれ広がることばとして分けられる。この分類から今回のデータをみると、「関東全域」に広がることばが「東関東」、「西関東」に比べて共通語と認識されている傾向が強い。使用の頻度でも同じことが言え、「東関東」、「西関東」は極端に少ない。
この結果はおおむね予想通りだった。埼玉県出身の私もこのデータの平均値にほぼ合致した形となった。
最後に気になったことだが、「かたす」、「〜じゃん」に関してはかなりばらつきがみられること、特に「〜じゃん」については、テレビなどで神奈川方言であるとかの情報が備わっていたのか、使用頻度の割りには認識度が低いということが気になった。これは今後の調査の対象となりえると思う。
最後のそれぞれのことばの意味を
「うっちゃる」→「捨てる」 「かたす」→「かたづける」 「かっけー」→「かっこいい」 「〜っきゃない」→「〜しかない」 「しょっぱい」→「塩辛い」 「〜じゃん」→文の最後について強調・疑問 「〜け」→「〜かい?」 「おもしー」→「おもしろい」 「なから」→「かなり」
このページのトップへ
日本大学文理学部 2004年度フィールドワーク入門